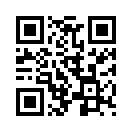› だにだらもんでⅡ ~しあわせリング工房「アトリエ・フィロンドール」~オーダーメイド・ブライダル・リフォームジュエリー静岡 浜松 › その他ジュエリー関連 › Filondor情報 › 工房作業 › 鍛冶屋のお祭り、金山祭・鞴 祭 (ふいごまつり)
› だにだらもんでⅡ ~しあわせリング工房「アトリエ・フィロンドール」~オーダーメイド・ブライダル・リフォームジュエリー静岡 浜松 › その他ジュエリー関連 › Filondor情報 › 工房作業 › 鍛冶屋のお祭り、金山祭・鞴 祭 (ふいごまつり)2012年12月11日
鍛冶屋のお祭り、金山祭・鞴 祭 (ふいごまつり)

鍛冶屋、金属加工業にはおなじみの金山祭の季節となりました。
鉱業、鍛冶など、金属に関する技工を守護する神様の金山彦神のお祭りで、火の神様にふいごの安全を祈る「ふいご祭」とも云うそうです。
昔、この「金山祭」の日には仕事が終わった後、宴会などを開くことがあったようですが今では神棚を作り、お酒と山海珍味、みかんをお供えするスタイルとなりました。
実は本来11月8日に行う風習でありますが、今年ついうっかり忘れてしまい、12月に入ってからお祭りしました。
金山様、ごめんなさい。

尾頭付きの鯛とみかん、お酒をお供えし参拝いたしました。
火と金属を扱う私達の仕事をこれからも見守って下さい。

金山祭・鞴 祭 (ふいごまつり)とは・・・・・ http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron14.pdf
「鞴」ふいごは金属加工に使う火を強くおこすために風を送る装置。
江戸では 旧暦の霜月 8 日(新暦でいうと 12 月初め) 鞴祭の日に、鍛治師・鋳物師・錺(かざり)師・時辰(とけい)師・箔打師など鞴を使って
金属加工をする職人たちが、お稲荷さんに供物とともにみかんを供える習慣があった。
別名「たたら祭」とも称し、仕事を休み、鞴を清めて注連縄を張り、祭壇に新穀・新酒・蜜柑・海の幸を供え祖神のご加護を感謝し、
火防・繁栄を祈願する祭りであった。蜜柑を満載して江戸へ運んだ紀伊国屋門左衛門 そして、この日の早朝、蜜柑をまいて
近隣の子供に拾わせる「蜜柑 江戸時代の千石船の絵馬 まき」の催しが繰り広げられた。
この鍛冶屋の鞴祭に必要なみかんを嵐の中 紀州から運んだ豪商紀伊国屋文左衛門。
「沖の暗いのに白帆がみえる あれは紀の国蜜柑船」の紀伊国屋文左衛門である。
また、日本画家 横山大観は この鞴祭の「みかんまき」の光景を活き活きと書いた絵があるという。
鞴を使わなくなった現在でも、金属加工業者が奉る神社 鉄や金属加工と関係する神社(金山彦命や天目一箇命,
金屋子神などを祭神とする神社)では、年に一度 この鞴祭の祭礼に火床を設けて火を起こし鞴で風を送る「金山祭 鍛錬式」
または「火入れ式」が行われる。
霜月8日を陰暦のまま行うところと新暦の11月8日、或いは季節感から月遅れの12月8日に開催されるところなどがあり、
今も各地でこの祭礼が鉄・金物を扱う商工業者を中心に行われている。
鞴祭りの起源は、15世紀の中頃、当時、鉄砲鍛冶の中心であった堺の鍛冶屋が伏見稲荷の御焚の火(霜月8日)に、
お礼をうけて鍛冶場に祀る風習が、稲荷信仰と一体となって地方へと拡散したという。
そのルーツは定かでないが、次のように語られている。
鍛冶屋、鋳物師、石工など鞴を使う職人たちは、旧暦 11 月 8 日を鞴祭と呼び、この日は、一日中、仕事を休み、
鞴を清めて、お神酒、赤飯、ミカンなどを供え、守護神の稲荷神を祭った。
この行事は、昔、三条小鍛冶宗近が刀を打つとき、稲荷神が現れて相鎚を打って助けたとか、 この日の卯(う)の刻に
天からたたらが降ってきたので、その記念に祭るのだと伝えている。
こちらから引用しました。⇒http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron14.pdf
江戸では 旧暦の霜月 8 日(新暦でいうと 12 月初め) 鞴祭の日に、鍛治師・鋳物師・錺(かざり)師・時辰(とけい)師・箔打師など鞴を使って
金属加工をする職人たちが、お稲荷さんに供物とともにみかんを供える習慣があった。
別名「たたら祭」とも称し、仕事を休み、鞴を清めて注連縄を張り、祭壇に新穀・新酒・蜜柑・海の幸を供え祖神のご加護を感謝し、
火防・繁栄を祈願する祭りであった。蜜柑を満載して江戸へ運んだ紀伊国屋門左衛門 そして、この日の早朝、蜜柑をまいて
近隣の子供に拾わせる「蜜柑 江戸時代の千石船の絵馬 まき」の催しが繰り広げられた。
この鍛冶屋の鞴祭に必要なみかんを嵐の中 紀州から運んだ豪商紀伊国屋文左衛門。
「沖の暗いのに白帆がみえる あれは紀の国蜜柑船」の紀伊国屋文左衛門である。
また、日本画家 横山大観は この鞴祭の「みかんまき」の光景を活き活きと書いた絵があるという。
鞴を使わなくなった現在でも、金属加工業者が奉る神社 鉄や金属加工と関係する神社(金山彦命や天目一箇命,
金屋子神などを祭神とする神社)では、年に一度 この鞴祭の祭礼に火床を設けて火を起こし鞴で風を送る「金山祭 鍛錬式」
または「火入れ式」が行われる。
霜月8日を陰暦のまま行うところと新暦の11月8日、或いは季節感から月遅れの12月8日に開催されるところなどがあり、
今も各地でこの祭礼が鉄・金物を扱う商工業者を中心に行われている。
鞴祭りの起源は、15世紀の中頃、当時、鉄砲鍛冶の中心であった堺の鍛冶屋が伏見稲荷の御焚の火(霜月8日)に、
お礼をうけて鍛冶場に祀る風習が、稲荷信仰と一体となって地方へと拡散したという。
そのルーツは定かでないが、次のように語られている。
鍛冶屋、鋳物師、石工など鞴を使う職人たちは、旧暦 11 月 8 日を鞴祭と呼び、この日は、一日中、仕事を休み、
鞴を清めて、お神酒、赤飯、ミカンなどを供え、守護神の稲荷神を祭った。
この行事は、昔、三条小鍛冶宗近が刀を打つとき、稲荷神が現れて相鎚を打って助けたとか、 この日の卯(う)の刻に
天からたたらが降ってきたので、その記念に祭るのだと伝えている。
こちらから引用しました。⇒http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron14.pdf